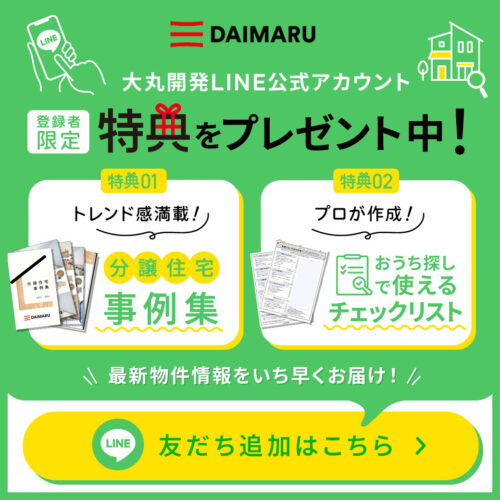2025/11/05
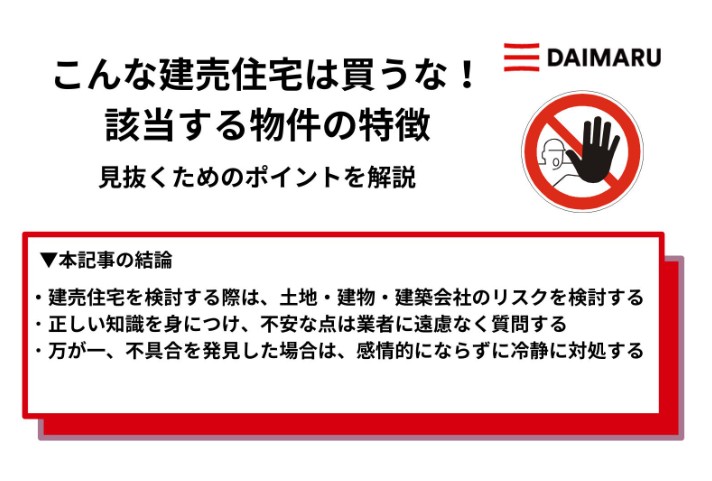
建売住宅の購入検討において、買ってから後悔しないかと不安を感じる方はいるのではないでしょうか?
一生に一度の大きな買い物で失敗し、損をしたと感じる事態は避けたいものです。
本記事では、不動産会社目線から「こんな建売住宅は買うな」に該当する物件の特徴を、「土地」「建物」「建築会社」の3つの側面から解説します。後悔しないための具体的なチェックポイントを知って、マイホームを選びましょう。
この記事を読み終えると、以下のようなメリットが得られます。
- 建売住宅の「土地・建物・建築会社」に潜む具体的リスクがわかる
- 契約前に損する物件を見抜くためのチェックポイントがわかる
- 万が一のトラブルが発生した際の対処法がわかる
読み終わるまでの目安時間:約7分
| ▼この記事を読んでわかること ●「こんな建売住宅は買うな」に該当する物件、土地、建築会社の特徴 ●後悔する物件を見抜くための具体的なチェックポイント ●万が一欠陥物件を購入した際の対処法 |
大丸開発は、岐阜地区で着工棟数16年連続No.1という実績を誇り、設立の昭和63年10月以来、地域に根差した確かな技術で家づくりを続けています。この長年の信頼と実績こそが、品質の証です。
デザイン性と高い機能性があるデザイナーズな分譲住宅を提供しています。無駄なコストを徹底的にカットし、物件の品質を保っています。
土地探しからも提案が可能です。岐阜県内で建売住宅を探している方は、現地を見学することから始めてみてください。
こんな建売住宅は買うな!に該当する物件の特徴

建売住宅を選ぶ際、内装や設備といった目に見える部分だけで判断してはいけません。以下のような特徴が見られる物件は、注意が必要です。
| ▼こんな建売住宅は買うな!に該当する物件の特徴 ●特徴①|日当たりが悪い ●特徴②|建物が傾いている ●特徴③|断熱や耐震の性能が不明確である ●特徴④|雨漏りや漏水の形跡がある |
特徴①|日当たりが悪い
日当たりの悪い物件は、湿気が溜まりカビや結露の発生リスクが高まるため、生活の快適性を損ないやすいです。カビによる健康被害や建材の腐食といった建物劣化を早めるリスクがあります。
また、日光が得られないと、昼間の照明費用や冬場の暖房費が増加し、全体の光熱費が上がってしまう点に注意が必要です。日当たりの悪さは、室内の明るさだけでなく、住民の気分にも影響を及ぼし、生活の質(QOL)を低下させてしまいます。
特に、物件の配置や周辺の立地条件により、冬場の日射量が不足するケースが少なくありません。
特徴②|建物が傾いている
完成したばかりの新築にもかかわらず、建物が傾いている物件は基礎や構造部分に深刻な欠陥が隠されている恐れがあります。
物件の傾きは、施工不良や地盤沈下など、重大な問題です。建物の傾きは壁や基礎に過度な負担をかけるため、建材のひび割れや破損といった急速な劣化を引き起こすでしょう。
また、ドアや窓の開閉が困難になるなど、日常生活に支障をきたす問題も発生します。欠陥が判明した物件は、市場評価が極端に下がるケースがあります。
特徴③|断熱や耐震の性能が不明確である
建売住宅の価格が安くても、断熱性や耐震性といった住宅の基本性能が不明確な物件は、注意する必要があります。その理由は、建築業者がコストカットのために、低品質な施工や材料を使っている場合があるためです。
耐震性が証明できない物件は、地震発生時の倒壊リスクや、家の傾きによる高額な修繕費用が発生するリスクが高いです。
また、断熱性能が低い物件は夏は暑く冬は寒いといった不快さに加えて、冷暖房効率が悪いため、高額な光熱費を負担し続けるでしょう。「住宅性能評価書」や「省エネルギー基準適合証明書」など、性能を数値で証明する公的な書類がない場合は、基本性能について疑問をもちましょう。
特徴④|雨漏りや漏水の形跡がある
新築の建物であっても、手抜き工事や欠陥工事により配管工事や防水処理などが上手くできていないケースがあります。
水漏れは、建物の耐久性や健康に影響を与える致命的な欠陥です。構造材の腐食を早める原因になりますし、湿気によるカビの発生で住民の健康を脅かします。
雨漏りが発生している場合は、配管工事や防水処理といった目に見えない部分の施工品質が全般的に低い恐れがあります。目に見えにくい点なので、天井や壁のシミ、異臭がないかを内見時に注意深く確認することが不可欠です。
こんな建売住宅は買うな!に該当する土地の特徴

土地は、建物と異なり後から変更できません。建売住宅を購入する上で、以下の点を慎重にチェックしましょう。
| ▼こんな建売住宅は買うな!に該当する土地の特徴 ●特徴①|浸水・土砂災害リスクが高いエリアにある ●特徴②|地盤改良工事の内容が不明瞭である ●特徴③|生活の利便性が低い ●特徴④|土地の境界が定まっていない |
特徴①|浸水・土砂災害リスクが高いエリアにある
浸水・土砂災害リスクが高いエリアに物件を建てるのは、リスクが高い行為です。地震だけでなく、近年増加している水害や土砂災害などにより、物件が倒壊または流失するため、命の危険すら伴います。
また、災害が発生した場合、建物の修繕費用だけでなく、生活再建自体が困難になる危険性があります。リスクの高い土地は仕入れ値が低いため、物件価格が安くなっている場合もあるため、価格の安さだけに惑わされてはいけません。
特徴②|地盤改良工事の内容が不明瞭である
地盤が弱い土地の場合、適切な地盤改良(地盤補強)が建物の安全性に直結します。この内容が不明瞭な物件は、手抜き工事やコストカットの温床になっている可能性が高いです。
地盤沈下や不同沈下(建物が不均一に傾くこと)が発生すると、高額な修繕費用がかかります。
また、建物の傾きは日常生活に支障をきたすだけでなく、建物の資産価値を大きく下げてしまう要因です。契約前に、地盤調査の結果と改良工事の施工記録について、書面で詳細な説明を求めましょう。
特徴③|生活の利便性が低い
価格が安い土地は、駅やスーパー、病院などから遠いなど、生活インフラから離れた場所に位置しているケースがあります。生活インフラが周辺にない立地は、毎日の生活の利便性を大きく低下させるため、購入後に生活の質(QOL)の低下を招くことになりかねません。
利便性の低いエリアは、市場の需要が限られるため、将来的な資産価値が下落しやすくなる点もデメリットです。建物価格が安くても、毎日の移動コストや時間コストが増加すると、総合的な支出で損をすることになるでしょう。
特徴④|土地の境界が定まっていない
土地の境界線が確定していない場合、購入後に隣人トラブルや予期せぬ出費を招くケースがあります。特に、隣の家の植栽やフェンスが自分の敷地に入っているといった越境問題で揉めごとが起きやすくなります。土地の境界関連のトラブルを解決するためには、境界確定の手続きが必要です。
しかし、この手続きは一度発生すると、解決までに時間と費用がかかってしまいます。具体的には、土地の確定測量費用や越境物撤去費用といった予期せぬ出費を自身が負担する可能性があります。
こんな建売住宅は買うな!に該当する建築会社の特徴

建売住宅の品質は、建築会社と売主の姿勢に大きく左右されます。以下の特徴をもつ業者は、コストカットや責任回避を優先する傾向があるため、損をしないためには避けるべきです。
| ▼こんな建売住宅は買うな!に該当する建築会社の特徴 ●特徴①|非常に安い金額を提示してくれる ●特徴②|契約や引き渡しを異常に急いでくる ●特徴③|書類の開示を拒否する ●特徴④|アフターサービスの内容があいまいである ●特徴⑤|施工期間が4ヶ月未満である |
特徴①|非常に安い金額を提示してくれる
相場を大きく下回る安さは、建物の品質や安全性を犠牲にしたコストカットの結果である可能性が高いです。安さの裏側には、低グレードの建材や設備の採用、もしくは下請け業者への過度なコストダウン要求が隠されている場合があります。
結果として、早期に故障や交換が必要となり、修繕費用がかさむことにつながりやすいです。目先の安さに惑わされると、最終的な総コストで損をすることになりかねません。
しかし、安価な物件がすべて危険というわけではありません。大丸開発は、流通・中間マージンといった無駄なコストを徹底的にカットして、高品質ながらリーズナブルな建売住宅を提供しています。
土地とセットで物件を提案できるため、気になる方は現地見学から始めましょう。
特徴②|契約や引き渡しを異常に急いでくる
優良な業者は、高額な買い物である住宅について、顧客が納得いくまで説明する時間を設けるのが一般的です。なぜなら、十分な説明なく契約を進めると、後々のトラブルや高額な費用負担につながりやすいからです。
異常に契約や引き渡しを急ぐ業者は、顧客が欠陥や契約書の不利な条項に気づく前に手続きを完了させたいと考えています。
「今すぐ決めないと他の方に取られる」といった焦りを煽る営業トークを多用する業者には注意しましょう。冷静な判断力を奪い、後悔につながる契約を結ばせてしまう危険性があります。
特徴③|書類の開示を拒否する
住宅の品質を客観的に証明する書類として、地盤調査報告書や検査済証(建築確認の完了検査書類)、住宅の性能評価書などがあります。
そのような書類の提示を拒否したり、「後で渡します」とあいまいにしたりする業者は、不利な情報や欠陥を隠しているリスクが高いです。特に、地盤や構造の安全性にかかわる情報をごまかしている可能性があります。
これらの書類の提示をしぶるのは、購入者の「損をしたくない」という思いを軽視しているサインです。
特徴④|アフターサービスの内容があいまいである
住宅に自信のある業者は、長期にわたる保証と充実したアフターサービスを具体的な書面で提供するのが一般的です。そのため、保証期間が法律で定められた最低限の10年のみであったり、対応範囲や連絡体制が不明確であったりすると危険なケースがあります。
後になって揉めないように、アフターサービスの内容は書面で細部まで明確にすることが大切です。構造上の欠陥や雨水の侵入以外の箇所(内装や設備)などについても、具体的な保証期間と対応内容が明記されているか確認しましょう。
特徴⑤|施工期間が4ヶ月未満である
建売住宅の標準的な工期は、最低でも4〜6ヶ月程度が目安です。この期間を極端に短縮している場合は、手抜き工事につながるリスクが高まります。現場監督による品質管理が不十分になり、配筋や断熱材の施工ミス、防水処理の不徹底といった欠陥が起きる原因です。
建売住宅の工期を短縮することは、業者にとってはコスト削減になりますが、購入者にとっては危険性が増す行為です。不動産の知識がなくても、契約前に工期の長さは必ず確認しましょう。
後悔する可能性が高い建売住宅を見抜くためのチェックポイント

「建売住宅を購入する際に損をしたくない」と考えるなら、業者任せにせず、契約前に物件と業者を自分で評価することが大切です。
以下のチェックポイントを参考に、欠陥物件を契約前に見分け、購入候補から確実に取り除きましょう。
| ▼後悔する可能性が高い建売住宅を見抜くためのチェックポイント ●ポイント①|ハザードマップを確認する ●ポイント②|内見時に施工品質レベルを見る ●ポイント③|建築会社の評判・口コミをチェックする |
ポイント①|ハザードマップを確認する
地震や水害に対する安全性と基礎的なリスクを確認することは、建売住宅選びの基本です。自治体が公開しているハザードマップで、物件が「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」に該当していないかをチェックしましょう。
▼ハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/
登録せずに無料で利用できます。
また、建築会社に地盤調査報告書の提出を求めることが大切です。地盤の強度や改良工事の有無・内容について、確認できると土地の安全性を客観的に評価できます。
ポイント②|内見時に施工品質レベルを見る
目に見える部分から、施工品質のレベルを推測することをおすすめします。簡単にできるのが、建物の傾きチェックです。ビー玉やスマホアプリなどで床の傾斜を計測できます。
また、施工の雑さは壁や天井の入隅(角)、フローリングや階段のつなぎ目に隙間やズレがないかといった細かい仕上げで確認します。
加えて、床下や天井裏の点検口があるかをチェックしましょう。点検口がない場合、配管の漏れや断熱材の不具合を確認するために、壁や床を壊す大掛かりな工事が必要です。
ポイント③|建築会社の評判・口コミをチェックする
契約前に建築会社や売主の過去の実績や評判を確認することは、引き渡し後のトラブルを防止するために大切です。建築会社の実際の品質管理体制やアフターサービスの対応、契約の誠実さについて、第三者や過去の購入者の客観的な評価をチェックしましょう。
情報収集の方法は多岐にわたります。具体的には、建築会社の公式サイトを見て施工実績を確認することが大切です。また、SNSを使って建築会社を調べることも有効です。
特に、アフターサービスに関する評判・口コミを重視してください。その会社が長期的に責任をもつ姿勢があるかどうかについて判断できます。
こんな建売住宅は買うな!に該当する物件を万が一購入してしまったら?

「こんな建売住宅は買うな」に該当する物件を万が一購入しても、以下のステップで対応することで、予期せぬ出費やトラブルを回避できる場合があります。
| ▼こんな建売住宅は買うな!に該当する物件をする際の対処法 ●ステップ①|契約書と保証内容を徹底確認する ●ステップ②|建築会社や売主に正式に通知する ●ステップ③|交渉が難航したら専門機関に相談する |
決してパニックにならずに、対応を進めることが大切です。
ステップ①|契約書と保証内容を徹底確認する
建売住宅の不具合を発見したら、冷静に自身の権利と保証範囲を確認することが大切です。感情的に業者に連絡する前に、以下の事実を整理しましょう。
- 発見した不具合を日付入りで写真や動画に記録し、証拠として保管
- 住宅瑕疵担保履行法にもとづく、10年保証の対象範囲と期間を再確認
- 契約書に記載されたアフターサービスの具体的な期間と対応範囲を確認
これらの情報をまとめることで、業者との交渉を優位に進められる場合があります。
ステップ②|建築会社や売主に正式に通知する
保証期間内であることが確認できたら、口頭ではなく記録が残る方法で業者に連絡し、補修を要求します。建売住宅の不具合の証拠や保証内容を確認した後、電話やメールで建築会社に先に補修を依頼しましょう。
業者側の対応が遅い、または不誠実な場合は、内容証明郵便といった記録が残る方法で正式に通知し、補修を要求するのがおすすめです。補修作業に取りかかる前に、原因究明と具体的な補修内容について合意し、後からトラブルにならないように書面で残します。
ステップ③|交渉が難航したら専門機関に相談する
建売住宅の業者が補修を拒否したり、不誠実な対応を続けたりする場合は、第三者の専門機関に介入してもらうことをおすすめします。専門機関に相談することで、法的な根拠にもとづいた解決ができるからです。
業者と話し合っても解決しない場合、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)といった住宅専門の紛争処理機関に相談しましょう。この機関は、住宅に関するトラブル解決を目的としており、公正な立場でアドバイスやサポートを提供する公的機関です。
作成された報告書をもとに、改めて業者と交渉するか、紛争処理機関の調停・仲裁などの手続きを検討しましょう。
大丸開発は、土地探しから建築、購入後のサポートまで一貫して対応します。徹底したコスト削減により、高品質でありながら手の届きやすい建売住宅を提供できる点がメリットです。
現地見学で、物件の品質やデザイン、ゆとりのある空間を直接確認できるため、気になる方は下記をチェックしてください。
まとめ|こんな建売住宅は買うな!は正しい知識を身につけて回避しよう
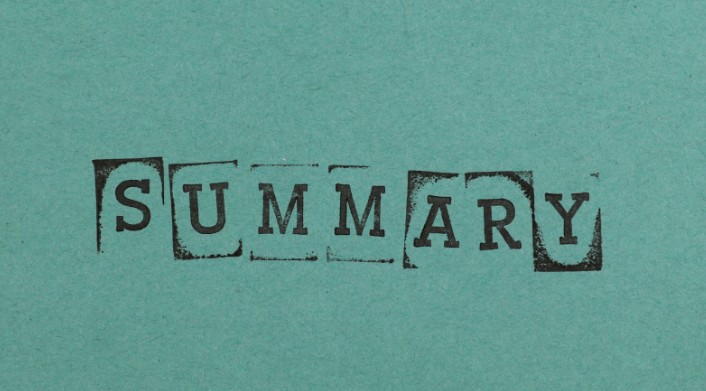
- 建売住宅を検討する際には、「土地」「建物」「建築会社」のリスクを検討する
- 正しい知識を身につけ、不安な点は業者に遠慮なく質問する
- 万が一、不具合を発見した場合は、感情的にならずに冷静に対処する
損をしたくないあなたの思いを確かな安心に変えるため、本記事で得た知識をもって、信頼できる業者選びを進めてください。
大丸開発は、土地探しから建築、購入後のサポートまで一貫対応しています。岐阜県内の分譲住宅を豊富に取り揃えているので、気になる方は現地見学から始めることをおすすめします。