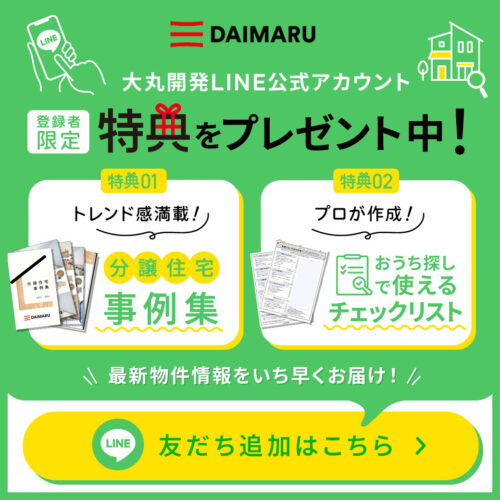2025/09/01
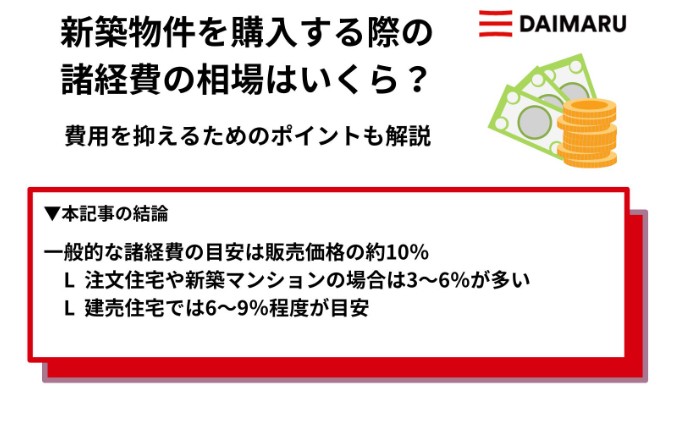
新築物件を購入する際、多くの人は土地や建物の価格ばかりに注目しがちですが、実際には「諸経費」と呼ばれるさまざまな費用がかかります。この費用には、仲介手数料や登記費用、税金、保険料などが含まれ、数百万円になるケースも珍しくありません。
事前に把握しておかないと、予算を大幅にオーバーしてしまう恐れがあります。しかし、諸費用の中には自分で手続きすると、数万円〜数十万円を節約することが可能です。
本記事では、新築購入時に発生する諸経費の相場や内訳、そして賢く節約する方法について、初めての方にも分かりやすく解説します。
この記事を読み終えることで、あなたが得られるメリットは下記の通りです。
- 新築物件の購入にかかる諸経費の相場を把握できる
- 新築物件にかかる主な諸経費の内訳を具体的に理解できる
- 新築物件の諸経費を賢く抑えるための具体的なポイントが分かる
読み終わるまでの目安時間:約10分
| ▼この記事を読んで分かること ●新築物件の購入にかかる諸経費の相場 ●新築物件にかかる主な諸経費の内訳 ●新築物件の諸費用を抑えるためのポイント |
大丸開発は、洗練されたデザイン性と高い機能性を兼ね備えたデザイナーズ分譲住宅を提供しています。無駄なコストを徹底的にカットし、高品質ながらリーズナブルな価格です。
また、土地探しからの提案もできるため、気になる方は現地を見学することから始めてみてください。
新築物件の購入にかかる諸経費の相場はいくら?

新築物件購入時の「諸経費」とは、物件本体価格以外に必要となる費用の総称のことです。主に、税金(登録免許税・不動産取得税・印紙税)や火災保険料、仲介手数料などが含まれます。
一般的な目安は販売価格の約10%ですが、物件タイプにより異なります。注文住宅や新築マンションの場合は3〜6%が多く、仲介手数料が不要なケースが中心です。
一方、建売住宅では6〜9%程度が目安です。土地と建物をセットで購入する場合や不動産仲介を介する場合は、仲介手数料や税金が多く発生しやすく、諸費用が高めになります。
土地と建物の価格を3,000万円と仮定した場合、多めに見積もると約300万円が諸費用として必要になるため、支払総額は約3,300万円です。諸費用は余裕をもって見積もっておくことが、後悔しない家づくりの第一歩と言えます。
具体的な2つのシミュレーション
まず、注文住宅を土地から購入する場合をシミュレーションします。
建物3,000万円、土地1,000万円を土地仲介ありで取得する場合、約183万円の諸経費が発生したとします。具体的な内訳は、下記の通りです。
| 項目 | 概算金額 |
| 土地仲介手数料 | 約40万円 |
| 登記 | 約35万円 |
| 税金 | 約18万円 |
| ローン費 | 約60万円 |
| 保険料 | 約20万円 |
| 合計 | 約183万円 |
また、建売住宅で土地と建物を3,500万円で購入する場合は、合計約295万円(約8.4%)が諸経費としてかかります。詳細は下記の通りです。
| 項目 | 概算金額 |
| 土地仲介手数料 | 約122万円 |
| 登記 | 約30万円 |
| 税金 | 約28万円 |
| ローン費 | 約75万円 |
| 保険料 | 約20万円 |
| 合計 | 約295万円 |
建売は土地・建物双方に仲介手数料や税金がかかるため、諸費用が高くなりやすくなります。
新築物件にかかる主な諸経費の内訳

新築物件にかかる主な諸経費の内訳は、下記の通りです。
- 契約・手続き時に発生する諸費用
- 住宅ローン借入れ時に発生する諸費用
- 物件引き渡し・登記時に発生する諸費用
- 新築物件を取得・入居した後にかかる諸経費
①契約・手続き時に発生する諸費用
まず、契約・手続き時に下記の諸費用が発生します。
- 手付金
- 印紙税
- 仲介手数料
- 設計料や地盤調査費用・地盤改良費用(注文住宅の場合)
具体的に見ていきましょう。
手付金
新築物件を購入する際、ハウスメーカーや工務店と売買契約を結ぶためには、購入価格の一部を手付金として先に支払う必要があります。
手付金の相場は購入価格の5〜10%で、支払いは現金が基本のため、契約前にはまとまった現金を用意しておくことが重要です。
なお、自己都合による契約解除の場合、手付金は返金されません。例えば、4,000万円の物件で契約を取りやめると、最低でも200万円(4,000万円×0.05)が戻らない計算になります。
大きな損失を避けるためにも、物件購入は十分に時間をかけ、慎重に判断することが大切です。
印紙税
新築物件に限らず、不動産売買契約を結ぶ際には印紙税がかかります。印紙税とは、契約書や領収書などの文書に課される国税で、金額や文書の種類に応じて印紙を購入・貼付し納付します。
新築の場合、代表的なものは「不動産売買契約書」(ハウスメーカーや工務店との契約)と「工事請負契約書」(工事業者との契約)の2種類です。
印紙税額は、下記のように軽減税率が適用されます。
| 売買価格 | 軽減税率適用の印紙税 |
| 500万~1000万円以下 | 5,000円 |
| 1000万~5000万円以下 | 1万円 |
| 5000万~1億円以下 | 3万円 |
また、注文住宅では土地売買契約書も作成する必要があるため、その分の印紙税がさらに追加されます。
仲介手数料
不動産を仲介業者を通じて購入する場合、仲介手数料が必要です。物件価格が400万円を超える場合は、以下の計算式で仲介手数料の上限が設定されます。
▼仲介手数料の上限の計算式
| 物件価格×3%+6万円+消費税=仲介手数料の上限 |
※2025年8月時点
※参考:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
例えば、3,000万円の新築物件を購入する場合、3,000万円×3%+6万円+消費税=1,056,000円が仲介手数料の上限です。
実際には売主や仲介会社との交渉で手数料が割引されるケースもありますが、購入資金計画を立てる際には上限額を想定しておくと安心できます。
設計料や地盤調査費用・地盤改良費用(注文住宅の場合)
注文住宅を建てる際には、建物本体価格以外に設計料や地盤関連費用が発生します。設計料は、間取りやデザインの作成、構造計算など専門的な業務に対する費用で、一般的には建築費の2〜15%が相場です。
一方で、地盤調査費用は、建設予定地の地盤の強さや性質を確認するためのものです。スウェーデン式サウンディング試験を使用すると、費用は一般的に5万円〜30万円程度かかります。
調査の結果、地盤が弱いと判定された場合には、地盤改良工事が必要となり、改良費用は30〜200万円程度かかる場合があります。
調査するまで、その土地の地層や状態の良し悪しは判断できません。地盤改良が必要かどうかで、費用が大きく変わる可能性があります。
②住宅ローン借入れ時に発生する諸費用
新築購入では住宅ローンの利用が多く、ローン契約に伴い各種の諸費用がかかります。代表的なものは、印紙税と融資手数料です。
印紙税は借入額によって異なり、おおよそ1万円〜10万円が相場ですが、電子契約であれば不要です。
融資手数料は金融機関や商品タイプによって異なり、定額型なら一般に3万〜5万円、定率型なら借入額の約1〜2%(税込)が目安です。一般に定率型は保証料不要、定額型は別途保証料が発生する場合があります。
(参考:フラット35「金融機関」と「商品タイプ」の選択)
住宅ローンを選ぶ際は、金利や返済条件だけでなく、このような手数料や付帯費用も含めて比較検討しましょう。
③物件引き渡し・登記時に発生する諸費用
物件引き渡し・登記時には下記の費用がかかります。
- 固定資産税清算金
- 火災保険料
- 地震保険料
- 修繕積立基金
- 登録免許税
- 司法書士への支払い
固定資産税清算金
固定資産税清算金は、不動産売買において売主と買主の間で、その年の固定資産税を日割りで精算するための費用です。固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、1月2日以降に売却した場合売主に請求が届きます。(参考:公益財団法人「不動産流通推進センター」)
引渡し日以降に住む買主が負担すべき分を「清算金」として、買主が売主に支払う仕組みです。下記の計算式をもとに算出されます。
▼固定資産税清算金の計算式
| (年間固定資産税額÷365日)×引渡し日から年末までの日数=固定資産税清算金 |
※2025年8月時点
相場は物件の評価額や土地面積、建物規模によって異なりますが、数万円〜十数万円程度になるケースが多いです。固定資産税清算金は契約時の重要な精算項目の一つであり、事前におおよその金額を確認しておくと安心できます。
火災保険料
新築物件を購入する際、多くの方は住宅ローンを利用し、その条件として火災保険の加入が義務付けられています。火災保険は、火事や火災などによる損害が発生した際、修理費用を保険金で補償する重要な制度です。
ただし、加入には保険料の支払いが必要です。金額は延べ床面積、建物の構造、契約期間、補償内容(保険金額や地震保険の有無など)によって変動し、一般的には10万円前後が相場です。
ただし、契約期間を長く設定する場合や補償を手厚くする場合は費用が高くなります。
地震保険料
日本は世界有数の地震多発国であり、多くの方が新築購入時に地震保険に加入します。仮に新築住宅が地震で半壊・倒壊しても、住宅ローンの返済義務は免除されないため、修繕や再建に備える必要があります。
そのため、新築物件購入時には、災害後の修繕費用の一部を補償する地震保険への加入がおすすめです。保険料の相場は年間約2万円ですが、建物の構造や補償内容だけでなく、特に所在地によって金額が大きく変わります。
地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険とセットで加入する仕組みです。また、補償額は火災保険の約半分が上限で、建物と家財をそれぞれ別契約する必要があります。
安心のためにも、保険内容を確認し無理のない補償プランを選びましょう。
修繕積立基金
修繕積立基金とは、新築マンションを購入する際に請求される費用のことです。将来の大規模修繕に備えて入居時に一括で支払います。
この費用は毎月支払う修繕積立金とは別で、購入時のみ発生します。外壁塗装や屋上防水、設備更新など、長期的な修繕計画に必要な初期資金として活用されます。
金額は物件の規模や設備、戸数によって異なりますが、一般的な相場は20〜100万円程度です。高級仕様や大型マンションでは、さらに高額になる場合もあります。
修繕積立基金は管理組合の財政を安定させ、将来の急な負担増を避けるための重要な制度です。購入時には必ず確認しましょう。
登録免許税
新築物件を購入する際には、土地と建物それぞれに対して所有権登記の手続きが必要です。登記の種類ごとに登録免許税が課税され、税額は「課税標準価格×税率」で算出されます。
新築戸建ての場合、主な税率は以下の通りです。(国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」を参考に記載)
- 土地の所有権移転登記:評価額×2%
- 建物の所有権保存登記:評価額×0.4%
また、登記申請時に不動産所在地の市町村が発行する証明書を添付すると、軽減税率が適用され税額が下がる場合があります。登記は司法書士へ依頼するのが一般的ですが、その報酬も別途必要になるため、購入時の諸費用に含めて計画しておくことが大切です。
司法書士への支払い
新築物件購入時に必要な登記手続きは、法律上は個人でも対応できます。しかし、必要書類が多く手続きも複雑で専門知識を要するため、初心者が自力で対応するのは難しいのが実情です。
そのため、ほとんどのケースでは司法書士に依頼します。司法書士に依頼する場合の費用は、依頼する登記の種類や事務所の料金体系によって異なります。
土地・建物の所有権登記や抵当権設定登記など、すべてを依頼した場合の相場は20万円程度とされています。購入時の諸費用に占める割合も大きいため、見積もり段階で司法書士費用も含めて資金計画を立てておくことが重要です。
④新築物件を取得・入居した後にかかる諸経費
新築物件を取得・入居した後にかかる諸経費は、下記の通りです。
- 家具・家電の費用
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 都市計画税
家具・家電の費用
新築物件の購入を機に、デザインや間取りに合わせて家具や家電を新調する方がほとんどです。しかし、すべてを買い替えるとなれば、費用は数百万円にのぼる可能性があります。
たとえ一部の買い替えであっても、数十万円単位の出費は避けられません。中には、このような費用を住宅ローンに組み込む方もいますが、その場合は当然毎月の返済額が増加します。
新しい生活を快適にするための買い替えは魅力的ですが、本当に必要なものかを見極めることが重要です。予算を超えて購入してしまうと、後々家計を圧迫する原因になりかねません。
住宅購入時には、家具・家電の購入費も含めた総合的な資金計画を立て、無理のない範囲で計画的に揃えていきましょう。
不動産取得税
新築物件を購入し、土地や建物の所有権を登記すると、入居後に一度だけ不動産取得税が課税されます。税額は地域や延べ床面積、評価額などによって異なり、数万円から数十万円と幅があります。
計算式は以下のとおりです。
▼不動産取得税の計算式
| 課税標準額×4%=不動産取得税 |
※参考:東京都主税局
しかし、この課税標準額は購入価格ではなく、都道府県の固定資産課税台帳に記載された評価額が基準です。不動産取得税には軽減措置があり、条件を満たせば税額が減額される場合があります。
納税通知書が届いたら、すぐにお住まいの自治体へ確認し、軽減申請の手続きをすることが大切です。
固定資産税
新築物件を購入すると、毎年固定資産税の支払い義務が発生します。税額の計算式は以下の通りです。
▼固定資産税の計算式
| 土地や建物の評価額(立地や規模などを基に算出)×1.4%=固定資産税 |
※参考:東京都主税局
現在は、新築住宅に対して土地・建物それぞれに一定期間の軽減措置が適用される場合がありますが、期間が終了すると本来の税額に戻ります。滞納すると延滞金が発生するだけでなく、最悪の場合は不動産を差し押さえられる場合もあります。
毎年、必ず予算に組み込み、計画的に支払いを続けましょう。住宅購入時には、ローンや維持費とあわせて固定資産税も長期的な負担として考慮することが大切です。
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している場合に課される地方税で、都市計画事業や区画整理事業などの費用に充てられるものです。
固定資産税と同様に、土地や建物の評価額を基に算出されます。税率は自治体ごとに定められていますが、法律で上限が0.3%と決められています。
▼都市計画税の計算式
| 評価額×0.3%=都市計画税 |
※参考:東京都主税局
例えば、評価額2,000万円の不動産の場合、税率0.3%なら年間6万円の都市計画税がかかります。都市計画税は毎年課税され、納付方法は固定資産税と同じく年4回の分割納付や一括納付が可能です。
軽減措置が適用されるケースもあるため、所有する物件の所在地自治体のホームページや納税通知書で確認しましょう。
新築物件の諸費用を抑えるためのポイント

新築物件の諸費用を抑えるためのポイントを5つ紹介します。
| ▼新築物件の諸費用を抑えるためのポイント ●1.保険や保証を見直す ●2.司法書士に依頼せずに自分で登記する ●3.仲介手数料不要の物件を見つける ●4.補助金や税金に関する制度を活用する ●5.繁忙期に引越ししない |
上記のポイントを意識して、諸費用を節約しましょう。
ポイント①|保険や保証を見直す
保険や保証は、自身の生活スタイルや住宅環境に合わせた必要最低限の補償内容に絞り、不要な特約を外すことで、無駄な保険料を抑えられます。
また、契約期間にも注目しましょう。例えば、火災保険や地震保険では、10年などの長期契約を一括で支払うと、年払いよりも割安になるケースがあります。
長期契約は更新の手間も省け、トータルの支払額を軽減できるメリットがあります。
ただし、一括払いは初期費用が大きくなるため、資金計画と合わせて検討が必要です。
ポイント②|司法書士に依頼せずに自分で登記する
不動産取得時には、所有権移転登記や住宅ローン利用時の抵当権設定登記が必要で、多くの場合は司法書士へ依頼します。
しかし、自分で手続きすると、司法書士に対する報酬を節約可能です。登記を自分で対応する場合、登記申請書類の作成や法務局への提出、必要書類の収集・確認などを実施する必要があります。
専門知識がある程度、求められ、手続きも複雑です。書類不備や記載ミスがあれば受理されない恐れもあるため、節約効果と手間のバランスを考慮して判断しましょう。
ポイント③|仲介手数料不要の物件を見つける
不動産購入時に発生する仲介手数料は、下記のように計算するため、数十万円~百万円以上になるケースもあります。
▼仲介手数料の計算式
| 物件価格×3%+6万円+消費税=仲介手数料の上限 |
※2025年8月時点
しかし、不動産会社が直接販売する「自社物件」や、売主から直接買える「売主直送物件」では、この仲介手数料が不要となる場合があります。仲介手数料がかからないだけで大きな節約になり、その分を家具やリフォームなどほかの費用に充てられるのは、メリットです。
物件探しの際は、仲介手数料不要の物件も視野に入れて検討すると良いでしょう。
ポイント④|補助金や税金に関する制度を活用する
新築住宅を購入する際は、各種の税金軽減制度を活用する方法は有効です。例えば、不動産取得税は、床面積や築年数などの一定の要件を満たす新築住宅であれば、軽減または非課税となる場合があります。
また、所有権保存登記や、特定の住宅ローンを利用する際の抵当権設定登記についても、税率が軽減される特例措置が設けられています。これらの制度を利用すれば、数万円から十数万円の節約ができます。
購入前に自治体や法務局で制度の詳細を確認し、最大限活用しましょう。
ポイント⑤|繁忙期に引越ししない
引越し費用を節約するには、繁忙期を避けることが効果的です。特に3月~4月や年末年始は引越し需要が集中し、料金が一年で最も高騰する時期です。
この時期を外すだけで、費用を大幅に抑えられる可能性があります。さらに、平日の引越しや比較的需要の少ない2月~5月頃を選べば、業者との料金交渉がしやすく、割引やサービス追加を受けられるかもしれません。
スケジュールに余裕がある場合は、閑散期を狙って計画を立てることで、同じサービス内容でも数万円単位の節約が実現できます。
大丸開発は、デザイン性と機能性を兼ね備えたデザイナーズ分譲住宅を提供する会社です。
徹底したコスト削減により、高品質でありながら手の届きやすい価格を実現。また、土地探しから建築、購入後のサポートまで一貫して対応し、理想の住まいづくりをトータルで支援します。
現地見学で、実際の住み心地やデザインの魅力を直接体感できる点も魅力です。
まとめ|新築物件の諸経費は10%を想定しよう

この記事のまとめ
- 新築購入時の諸費用は「本体価格以外の総費用」
- 目安は本体価格の約10%(注文住宅・新築マンションで3〜6%、建売で6〜9%)
- 手数料方式の比較・税制優遇・手続き工夫でコストダウンが可能
新築物件を購入する際は、諸経費を購入金額の約10%を目安に見積もっておくと安心です。本記事で紹介したポイントを実践すれば、諸経費を抑えることができ、無理のない資金計画が立てられます。
まずは自分で対応できるところから少しずつ始めてみましょう。